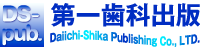お知らせ
 編集長のブログ67 今季巨人阪神戦初観戦 - 2018.03.31
編集長のブログ67 今季巨人阪神戦初観戦 - 2018.03.31
阪神先発は若きエースの藤浪投手、巨人先発は阪神キラーとされる田口投手でした。
田口投手は、今日はかなり打ち込まれ、あまり調子が上がっていない感じでした。
対して、藤浪投手は球が走っていて、球速と球威は申し分ありませんでした。
ただ、課題の制球の面からの崩れが・・・との感じで、6回途中で降板してしまいました。

結果、後続の投手の調子もあって巨人が勝ちましたが、先発投手の出来としては藤浪投手のほうが上だったと私は思います。(巨人は、メジャー帰りの上原投手を抑えとして起用し、大喝采を浴びていました。)
藤浪投手と言えば、かねてより歯並びと咬合の問題が注目されています(私たち歯科関係者からは)。今こそ、歯科の出番!ではないでしょうか。
弊社は、咬合の問題が如実に結果に表れるという点で、スポーツ歯学に注目しています。この分野を掘り下げることで、咬合学の真髄に迫ることが可能ではないかとも考えています。
今後も出版活動のうえで、是非探求していきたいです。
 編集長のブログ66 『日本農業新聞』を知っていますか - 2018.03.20
編集長のブログ66 『日本農業新聞』を知っていますか - 2018.03.20

農業に特化した専門紙なので、一般の全国紙と比べても、格段に内容の深い記事作りになっています。農業関係者でなくても興味深い、楽しい記事もたくさん掲載されています。たとえば先日は、チコリという野菜の栽培方法から、美味しい料理法まで紹介されていました。
本日の紙面で、同紙が今日で創刊90周年を迎えたことを知りました。
農業人口が減少しているなかで、健闘されていると思います。

食は人間生活の基本であり、国民の健康を守る医療とも深く関わっています。
弊社の「季刊 歯科医療」は昨年で創刊31周年、まだ農業新聞の3分の1ほどの歴史ですが、専門に特化した強みを発揮するという点では、非常に刺激を受けます。
これからも、歯学図書専門出版社として、最大限に社会に貢献していくことができればと思っています。
 編集長のブログ65 いま再注目!「押着義歯」で患者さんに喜ばれる - 2018.03.17
編集長のブログ65 いま再注目!「押着義歯」で患者さんに喜ばれる - 2018.03.17

(本書表紙掲載の写真。正解は「良く噛める」のは右側。疑問の方は本書へ。)
単行本『押着義歯のすすめ』は現在も販売を続けているところ、先日本書をお買い求めになった読者の先生から、電話でうれしいご報告がありました。「押着義歯の技法で総義歯の患者さんの臨床を行ったら、とても喜ばれた。実は難しい患者さんで困っていたのだけれど、他の患者さんにも実施したところ同じように好評だった」とのことです。
患者さんが「これは具合が良い!」と驚き喜んでくれたそうですが、実際のところ治療にあたったこの先生ご自身が一番驚かれたそうです。「これで良かったのかぁ・・・」と思ったそうですが、読後にこのような連絡をいただけることが出版社としては一番うれしいです。
また、別の読者の先生からは先ごろ、「巻末の檜山隆一先生との師弟対談がとても良い。自分が檜山先生の立場になって読むと、長谷川先生に直接教えてもらっているようでよくわかる」とのご感想をいただきました。

(本書巻末の対談。本文の趣旨がよく理解できると好評です。)
本書の情報は全く古びていないことを強く感じます。
長谷川清先生はセミナーではおやじギャグを連発するなどお茶目なところもある先生でしたが、すべてサービス精神の現れなのです。亡くなられた後も、押着義歯で救われた患者さんと歯科医師の先生がいることを、何よりも喜ぶはずです。
空の上の長谷川先生! 先生の遺した押着義歯は、今も歯科医療の現場で生き続けていますよ!
「押着」と書いて「おうちゃく」と読みます。「押着は横着ならず」ですが、よく噛めてよくしゃべることができる義歯が簡単に作れますよ、との意味も込めているそうです。
総義歯で悩んでいたり、「苦手」と感じている先生方には、是非ご一読をお勧めいたします。
 編集長のブログ64 日歯連盟事件が冤罪ならば・・・春は来る - 2018.03.04
編集長のブログ64 日歯連盟事件が冤罪ならば・・・春は来る - 2018.03.04
係争中だった日歯連盟の迂回寄付事件で、今年1月22日、当時の会計責任者であった村田憙信先生に有罪判決が出されました(現在、控訴中)。
この事件については、私も歯科記者クラブの一員として、日歯連盟の記者会見など取材を続けさせていたいただき、経過を見守っていました。現在の高橋英登会長は人格的にも素晴らしい方で、日歯連盟側の言い分をさまざまな角度から検証することができました。
そうしたなかで私が明確に言えることは、これは私利私欲のために行った行為ではないということです。歯科界の発展のために、ひいては国民の健康を守るためという「大義」がそこには存在していました。政治的イデオロギーとは関係なく、政権を担い執行権を有する政党に働きかけて歯科の保険制度を守ることは、歯科界全体のためになると信じて行ったものでした。
確かに、脇が甘かったとは言えるかもしれません。政党に働きかけるという行為は、賄賂性が発生しやすく危険だという意見もあるでしょう。ただ、取材の過程で、違法なことは駄目であることくらいは日歯連盟の方々は熟知し、顧問弁護士に充分相談したうえで実行した寄付であったこと、そして顧問弁護士は現在でも「法律的にはなんら問題ない」と一貫して説明していることから、事件の深淵が見えてくるように感じます。

ここのところ暖かく、通勤経路で庭の桜が咲いているお宅がありました。
日歯連盟側は、村田先生以外の裁判も含め、今後も「無罪」を主張していきますが、無実であるということが当然の前提です。無実の人間が「有罪」判決を受けた時点で「冤罪」は確定します。冤罪は国が個人に行う最大の人権侵害であり、冤罪を晴らすことは国との戦いです。
現在、日歯連盟側は、もともとは国側にいた検察官を退官したいわゆる「ヤメ検」の弁護士を信頼しているようですが、僭越ながら私の本音を言わせていただければ、国と戦えるのは反体制派の反骨の気概を持った法律家でないと難しい面があるのではないかと思います。
日歯連盟の迂回寄付事件が冤罪であれば、必ず春は来ます。というか、皆の応援で冤罪をすすぎ、冬の時代を終わらせなければなりません。
「すすぐ」という言葉は「雪ぐ」と書きます。日歯連盟関係者の心を凍らせた事件の雪解けと春の到来を心から願っています。
 編集長のブログ63 スポーツ歯科推進議員連盟設立 - 2018.02.21
編集長のブログ63 スポーツ歯科推進議員連盟設立 - 2018.02.21
2020年の東京オリンピックに向けて、スポーツ歯科の推進が求められています。 弊社も本年1月発刊の『季刊 歯科医療2018年冬号』の特集で、「スポーツにおける歯科の重要性―スポーツ歯学の現場からの提言」を掲載し、各方面から好評をいただきました。
このたび、発起人である遠藤利明衆議院委員を会長として、橋本聖子参議院議員を顧問とする「スポーツ歯科推進議員連盟」が設立されました。 本日、参議院会館で設立総会が開催され、弊誌の特集編者である明海大学・安井利一学長の講演もあるため、早速取材に行ってきました。
スポーツと歯科の関連を考えたとき、咬合をはじめとする口腔の状況が如実に現れるのがスポーツ選手なのだなと思います。東京オリンピックで日本選手に活躍していただくために歯科界の担う役割は重要で、大きなチャンスです。そのためには国民に対するアピールが大切です。
また、弊誌冬号のスポーツ歯科の特集を安井先生とともに担当していただいた大阪大学特任教授・前田芳信先生は、今年に入ってから精力的に歯科医向けの講習会を開催し、スポーツデンティスト認定医を増やす活動を進めています。
本日の『スポーツ歯科推進議員連盟』設立総会を取材した実感として、本連盟の国会議員の方々の熱意も素晴らしいものがありました。何よりも、選手が本来の力を最大限に発揮して活躍できるために、また怪我や故障などのスポーツ障害から選手を守るために、歯科の力が必要なのだということです。
本活動のさらなる発展を期待するとともに、歯学図書専門出版社として縁の下からの後押しをさせていだきたいと考えています。
 編集長のブログ62 東京の大雪 - 2018.01.23
編集長のブログ62 東京の大雪 - 2018.01.23
天気予報どおり、午前中は氷雨が、昼過ぎから大粒の雪が降り始めました。写真でわかるように、植え込みに雪が積もり始めています。

帰宅時は吹雪です(下の写真)。札幌の街並みかと見まごうような風景です。
早めの帰宅と不要不急の外出を控えるように呼びかけているためか、車も人の通りも少なめです。駅では入場規制が行われ、改札口に向かうエスカレーターも停止されていました。
東京でも年に1、2回はこんな日があります。
一夜明けると、昨夜とうって変わって雲ひとつない青空が広がっていました。
がっちり滑り止めの付いた靴を履いて出勤しましたが、近隣の人たちが雪かきをし気温も暖かいため、ヒヤリとする場面もなく出勤できました。朝一での印刷会社からの車による書籍の納品も予定通り完了しました。お天気が良いため、積もった雪も程なく溶けるでしょう。
雪国の方たちから見れば笑われるような程度の雪で、交通網から何から大混乱の大都会。抗うことのできない自然の力の前には、人間が作り上げた文明がいかにもろいか。そんなことを考えさせられる大雪の1日でした。
 編集長のブログ61 2018年冬号の特集は「スポーツ歯科」! - 2018.01.22
編集長のブログ61 2018年冬号の特集は「スポーツ歯科」! - 2018.01.22
本ブログの今年初の更新です。早くも新年の誓い(今年はブログを、最低でも週に1、2回は更新しよう)を破ってしまいました(苦笑)。
過ぎたことは気にせずに(「少しは気にしろよ!」の突っ込みは置いといて)、今年も何卒よろしくお願いいたします。
早速ですが、今月10日、『季刊 歯科医療2018年冬号』が発刊されました。特集は「スポーツにおける歯科の重要性~スポーツ歯学の現場からの提言~」です。明海大学の安井利一学長と大阪大学大学院の前田芳信特任教授の編集により、この分野の第一人者による最新の情報が掲載されています。
東京オリンピックを控え、日本歯科医師会が力を入れている折からタイムリーな特集であり、改めて歯科の存在意義を国民にアピールする絶好の機会と捉えたいと思います。
歯科医療従事者のみでなく、実際にスポーツをされている選手や指導者の方々にとっても非常に有用な内容で、読者の評判も上々です。まだお読みでない方は是非お手に取ってご覧ください。


本号は、特集のみでなく、篠田鉄郎先生の「インプラント周囲炎」、清水英寿先生の「分子整合栄養医学」など、時代が求めている真実を追究した論文は大変興味深く見逃せません。もちろん佐藤貞雄・白数明義先生、松元教貢先生、舩津雅彦先生の連載は、安定した筆致で好調に論述を展開しており、多くの読者のご支持をいただいています。
これらにまつわるエピソードなども含め、本ブログでまたご紹介させていただきたいと思います。
私事ですが実は正月休み明け早々、風邪をひいてしまいました。かなり具合が悪いので、もしかしてインフルエンザで他の人たちに移してはいけないと思い、早めに病院に行きましたが普通の風邪とのこと。ただ、今年の風邪は治りが遅いです。皆様もどうぞお気をつけください。
 編集長のブログ60 神官の子孫ですがメリークリスマス! - 2017.12.23
編集長のブログ60 神官の子孫ですがメリークリスマス! - 2017.12.23
とてもよくできていますね。机の脇に置くと、たちまちクリスマスの雰囲気が出ます。

日本人は無宗教のため、キリスト教の祭日も抵抗なく受け入れると言われますが、私の家は曾祖父の代まで出雲大社の神官を務めた家系でした。つまり神道です。皇室の方々がミッション系の学校に行く時代ですから、私のような下々の民がクリスマスを祝っても何の問題もないとは思いますが。
先日、弊社を訪れた営業の男性は、母方が桜田門外の変で真っ先に切り付けられた井伊家の家臣で、父方が切り付けた水戸藩士であったとのこと。お見合いで出会って話を進めた段階でそれが明らかになり、両家が驚いたとか。今年はNHKの大河ドラマで『女城主 直虎』を放送しているため、身内の間では改めてクローズアップされているようです(笑)。
「そして生まれたのが私です」とのことで、「まるでロミオとジュリエットですね」「ハッピーエンドで良かったですが」と笑いました。
長州藩士と会津藩士の子孫が出会って結婚したという話も聞いたことがあります。先祖は仇同士であっても、いや逆に仇同士であったからこそ、強い縁で引き寄せられ結ばれるのだろうかと、感慨深く思いました。
イスラエルとパレスチナの問題などは、遠い日本で暮らす私たちでも、早く平和を取り戻してほしいと願っています。先祖や歴史を遡ると並々ならぬ確執があるとしても、未来に目を向け、過去や宗教にとらわれない平和な明日に向かいたいとつくづく思います。
 編集長のブログ59 目黒川のイルミネーション2017 - 2017.12.19
編集長のブログ59 目黒川のイルミネーション2017 - 2017.12.19
撮影日は一昨日の夜、風が強くとても寒い日でした。休日のあまり遅い時間帯でなかったためか、美しい川沿いの遊歩道を散歩する人たちが結構いて、人通りが途絶える瞬間を待ってシャッターを押しました。
私も少し歩いてみようかと思いましたが、風が冷たくて無理! 写真だけ撮って速攻で退散しました(笑)。

このイルミネーションが灯ると、今年も残すところわずか。年々と時の経過の速さを痛感するとともに、自分は今年は何ができただろうか・・・と、少しセンチメンタルな気分になります。
この2年あまり、ボランティア的な他人のためにする無償奉仕のような活動が、思いのほか多かったように思います。亡き父から教えられた座右の銘は「義を見てせざるは勇なきなり」。父の遺言は守れているかもしれませんが、自己犠牲するほどの力のある身か?と複雑です。
同時に「情けは人のためならず」という言葉も浮かびます。他人のために何かをすることは、結局自分自身のためになるということ。
少し意味は違いますが、今秋、郷里で同窓会があり、久しぶりに帰省しましたが、ホテルで同室になった友人からある助言を受けました。強く真剣な助言でした。そのおかげで、大げさに言えば九死に一生を得たような経験をしたのです。当初出席を迷いながらも、幹事の仕事を頑張ってくれた別の友人に申し訳なくて参加したのですが、本当に行ってよかったと思います。
他人のための無償の行為は、いずれはその人から何らかのお返しがあったり、そのとき得た人脈などから新しい鉱脈を得ることもあるかもしれません。しかし、見返りを期待しての行為はボランティアではないし、たとえ何の見返りがなくても、それをしたことで自分自身の能力や精神性を高めることができるのではないでしょうか。
人のために頑張ったことに無駄なことはない・・・と、改めて思います。
 編集長のブログ58 弊社が広告を取らない理由(わけ) - 2017.12.15
編集長のブログ58 弊社が広告を取らない理由(わけ) - 2017.12.15
時々、著者の先生や読者の方から、「広告を取らないで雑誌を発行して採算がとれるのか?」「会社がつぶれないのか?」などの疑問を率直にぶつけられます。

今は亡き長谷川清先生(弊社刊『押着義歯のススメ』の著者)は、ご自身のセミナーで、「第一歯科出版の経営がどうやって成り立っているのかが最大の謎。バックは山〇組か?」などとジョークを飛ばしていましたが、そのような大それたバックも何もありません(苦笑)。
真相は・・・というと、30年以上前の草創時はとにかく編集が忙しく、広告担当に社員を回す余裕がなかったのです。そのため当時は、編集に力を入れて良い出版物を発行し、広告収入をカバーするほうがよいと割り切りました。
その後、出版もデジタル化が進み、編集部の修羅場は改善されましたが、その時には既に「第一歯科出版は広告を載せない」という評判が広まり、スポンサー関係に気を使わずに本音の論文を書けるということで、「お宅は『暮らしの手帖』と一緒だね」と評してくださる先生もいらっしゃいました。
次号の2018年冬号に登場する篠田鉄郎先生もそうした先生方のお一人で、真実の情報を読者に伝えたいということで、1論文としては大作の19頁(印刷時)の原稿をお寄せくださいました。
出版社としての誇りの持ち方はさまざまです。広告を載せることが悪いことだとは思いませんし、弊社も今後、宗旨替えがあるかもしれません。
しかし、広告の有無の如何によらず、本当のニーズに応えた真実の情報を読者に届けることにかけては、誇り高くブレずに進んで行きたいと思います。