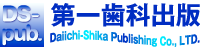編集長のブログ
 編集長のブログ54 歯科衛生士の復職の必要性 - 2017.11.10
編集長のブログ54 歯科衛生士の復職の必要性 - 2017.11.10
“歯科衛生士の復職支援の必要性”を説く
11月8日(水)第368 回中央社会保険医療協議会
第368 回中央社会保険医療協議会 総会中央社会保険医療協議会(第368回)が11 月8 日(水)、都内のTKPガーデンシティ竹橋で開催され、「調査実施小委員会からの報告」、「横断的事項(その4)」について議論が行われました。
「横断的事項(その4)」の議論では、「医療従事者の多様な働き方支援・負担軽減 医療従事者の常勤要件の見直し 医師以外」に関して、日本労働組合総連合会の平川則男委員は「安全で適正な医療を提供することが前提」としたうえで、「歯科衛生士については、要件緩和ではなく人員配置で対応すべき」との意見を述べました。
これに対して日歯常務理事の遠藤秀樹委員は、口腔管理において重要な役割を担っている歯科衛生士は、現状では歯科診療所の半数程度しか充足していない一方、出産等で職を離れ復職していない者が多数いると説明。そのうえで、「そういった歯科衛生士にパートなどでの復職を支援し、良質な歯科医療の提供を図ることが必要である。また、今回提示されている常勤要件の施設基準に係る診療項目については、歯科医師の他に医療専門職が共にいるという趣旨であり、パートの連携による人員配置でもその趣旨にかなう」との考えを示しました。
歯科衛生士のみでなく、看護師や保育士、また銀行員などお勤めをされていた方も、出産・子育て等で職を離れた女性の復職支援は、労働力不足を解消するうえでも、また女性のライフスタイルを応援する意味でも、現代社会の大きなテーマとなっています。
せっかくの資格やキャリアを眠らせていてはもったいないです。殊に歯科衛生士不足が叫ばれて久しい歯科界においては、いったん現場を離れた歯科衛生士の皆さんが現場に復帰しやすい環境作りを、是非とも推し進めていきたいものです。
 編集長のブログ53 ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2017 - 2017.11.08
編集長のブログ53 ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2017 - 2017.11.08
午後から、ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2017の授賞式を取材してきました。
ベストスマイル・オブ・ザ・イヤーは、国民の歯と口腔の健康作りから全身の健康を守る「8020運動」推進の一環として1993年から始まりました。
イチロー選手や黒木瞳さんなど、歴代の受賞者は素晴らしい笑顔の方々ばかりです。
今年の著名人部門の受賞者は米倉涼子さんと草刈正雄さんです。

お二人とも長身でスタイル抜群です。隣の「よ坊さん」の2.5頭身とは対照的ですね。
米倉さんはさすがの脚線美です。プレスは最前列に座れるのですが、客席からは「はぁ~、背が高いな~」との嘆息の声が漏れました。
ところで、米倉さんの衣装はどうなっているのだろう?という方のために、側方もわかる画像をもう1点。他の方ではなかなか着こなせないような、斬新なデザインが素敵ですね。

一般の方々のフォトコンテストは、お年寄りや子供たち、都会や自然に囲まれた地方など、さまざまなシチュエーションの中でとびきりの笑顔を撮影された写真が受賞します。

一般受賞者の皆さんも、米倉さんと草刈さん、写真家の浅井慎平さんら審査員の方々、日本歯科医師会の堀憲郎会長ら歯科医師会関係者らとともに、集合写真におさまりました。
こうした式典では大活躍のよ坊さん。お勤めを終えて退場となりますが・・・。

よ坊さんは、スタッフに支えられて動くのが大変なようです。
着ぐるみの中の人は視界も悪く、段差のあるステージから降りるのも危なっかしくて一苦労でした。トレードマークの歯ブラシも男性スタッフに持ってもらっていますね。
頑張れ、よ坊さん!心の中で声援を送らせていただきました(笑)。
 編集長のブログ52 19番がマウンドへ - 2017.10.18
編集長のブログ52 19番がマウンドへ - 2017.10.18
そもそも技術も状況も違いますから、松元先生はこれは私のレアケース、各先生はご自分で考えてほしい、という趣旨の言葉を常に述べています。
同じく弊誌で連載中の舩津雅彦先生は、昨年から「舩津教室―誰でもできる咬合治療」というセミナーを開催していますが、受講者に「私を疑え」と述べています。これは舩津先生の臨床の師である大坪建夫先生から常々言われた言葉だそうです。
師に教えを請うたり他者から学ぶことはとても大事なことですが、鵜呑みにするのは禁物で、自分の臨床は結局自分で作りあげて行くしかない、ということだと思います。
現に、大学の歯科教育では未だに抜歯矯正が主流ですが、それを疑ったことから大坪先生や舩津先生の矯正・咬合治療は始まりました。前述の松元先生にしても、世間が即時荷重に否定的な時期から、それに反し自分の信じた道を究めたからこそ、即時荷重インプラントの第一人者としての今があります。
ところで、昨夜はプロ野球のセ・リーグCSファースト最終戦、阪神が横浜に1対6で敗れました。藤浪晋太郎投手は6回から救援登板し、2回を無失点で抑える好投でした。

苦しんだシーズンでしたが、マウンドに立つ19番への球場全体がどよめくような歓声と拍手に、やはり特別な選手なんだなと改めて思いました。
かねてより私は、彼の歯並びと不正咬合が不調の原因のひとつで、体が大きくなったことで今季はその影響が如実に表れバランスを崩したと考えているのですが、舩津先生ら非抜歯矯正の臨床家ならば、23歳の藤浪投手に対してどのような咬合治療を行うのだろうかと、とても興味があります。
 編集長のブログ51 2017年秋号発刊間近 - 2017.10.07
編集長のブログ51 2017年秋号発刊間近 - 2017.10.07
本文はまだ折りごとにバラバラで、表紙はこれからPP加工をして光沢と強度を増します。

万が一ここで重大なミスが発見された場合は、その折(16頁単位)を刷り直さなければなりません。仮にそういうことがあっても(実際に時たまある)、製本後に気づくのではもっと大変なことになり、発送してしまってからは手遅れ・・・という事態になってしまいます。
最後まで手を抜かないチェックが大切になります。
落ち葉の写真をモザイクタイル状に加工した表紙の写真が、秋らしくてきれいですね。
特集は日大の今井健一教授の編集による「口腔管理と口腔微生物」です。国民の健康長寿に貢献するために、歯科医療従事者必須のテーマです。
連休明け早々の発売となります。是非お手に取ってご覧ください。
 編集長のブログ50 スポーツ選手と歯 - 2017.10.02
編集長のブログ50 スポーツ選手と歯 - 2017.10.02

先日、新聞のスポーツ欄に、プロ野球の勝利投手が口を大きく開けて喜んでいる写真が掲載されていました。素朴な好青年なのですが、どうしても歯並びに目が行ってしまいます。これでは口が閉じないのでは?と思ったところ、やはりプレー中も口元が開き気味の選手のようです。
弊社が贔屓の藤浪晋太郎投手(阪神)は、今シーズンは制球難に苦しみ思うような活躍ができませんでしたが、彼も前歯の前突と叢生が気になります。非抜歯の矯正治療を行えば、あるいは矯正が無理ならば適正なマウスガードの使用でも、咬合の改善は投球に必ず好影響を及ぼすはずです。
悩める若きエースに「原因のひとつは歯にある」ことを伝えたいし、社会の視線をもっと歯科に向けてもらうために、私たちのアピールが必要になってくると思います。
東京オリンピックを控え、日本歯科医師会もスポーツ歯科に力を入れています。歯や咬合が運動パフォーマンスに影響を与えることは、エビデンスに基づいて明らかになっています。
来年1月発行の「季刊 歯科医療」2018年冬号では、スポーツ歯科をテーマに特集を組みます。ご期待ください!
 編集長のブログ49 暑中お見舞いから残暑お見舞いへ - 2017.08.09
編集長のブログ49 暑中お見舞いから残暑お見舞いへ - 2017.08.09
先程、宅配便会社の方が配達に来ましたが、さすがに暑そうでした。外で活動する方や外出される方は、十分お気を付けください。
先日、いつもお世話になっている先生(の奥様)から、こんな可愛らしいペンギンの暑中見舞いをいただきました。

よくできた立体イラストで、ペンギン山と、その下の水槽で本当に泳いでいるように見えますね。右下の逃げ出そうとしている(?)一羽がまた可愛い。私たちの編集の仕事でも、真面目な硬さの中に、このようなちょっとした遊び心も大切だなと思わされます。
F先生(と奥様)、ほのぼのとした涼風を届けていただきありがとうございます。
ブログをお読みいただいている皆様には、ペンギン画像で残暑お見舞い申し上げます!
 編集長のブログ48 ロイテリ菌と西田亙先生 - 2017.08.03
編集長のブログ48 ロイテリ菌と西田亙先生 - 2017.08.03
本日、東京・ホテルニューオータニで「ロイテリヨーグルト」新商品発表会と、糖尿病専門内科医・西田亙先生のセミナーがありましたので、取材に行ってきました。
日本カバヤ・オハヨーホールデングスグルーブのヘルスケア領域に特化した事業会社「オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社」が昨年設立され、口腔内の細菌バランスを整えるヨーグルト「ロイテリヨーグルト」を今年9月19日から関東エリアで先行発売します。
ロイテリ菌は、日本ではまだなじみの薄い乳酸菌ですが、高い安全性と有益性から、今後は注目されること必至です。取材後は、ロイテリ菌含有のヨーグルトをお土産にいただきました。
下の写真は既に賞味後で、中は空です(笑)。とろりとした滑らかな食感で、ミルクの美味しさを引き出した食べやすい味わいでした。
西田先生の今日のお話のポイントは「炎症を鎮めれば、全身は健やか」「現代人の病は“炎症”すなわち“穢れ”からやってくる」でした。「日本は東京オリッンピックを迎えるにあたって、受動喫煙対策を考えるよりも、受動口臭対策をしたほうがいい。メチルメルカリブタンは青酸ガスに匹敵するのだから」と。
また、「外国人の7割は日本人の口臭にがっかりしている。しかし日本人の9割は無自覚である。自分も口臭があるからわからないのだろう。私も8年前は重度の歯周病でした。自分もかつては相当な口臭がしていました」とのことで、ご自身の体験を踏まえた説得力のあるものでした。 
さらに、「日本人を覚醒するキーワードは、“慢性微小炎症”です。体内の炎症状態を表す血清CRP(C Reactive Protein:C反応性タンパク)は、正常値は0.3mg/dLとされています。私の患者さんのケースで、歯周基本治療が完了したころから入院時の血清CRPは 0.35 mg/dLから0.16 mg/dLまでになり、半減していたのです。」
「歯医者さんは例えると、身体を清めてもらう神社です。口からやってくる穢れ(病気・炎症)を歯科医師(神主)と歯科衛生士(巫女)がお口と体の“お清め”をするところでしようか。お供え物は、“ロイテリヨーグルト”です。」と、上手にオチもつけられて、万雷の拍手を浴びていました。
腸の健康が認知症の予防にもつながると言われています。そのときに大事なのは入り口である口腔です。齲蝕が減っても、歯科医師の担う役割はますます重要なものになることを、将来的に実感させられました。
 編集長のブログ47 夏は素麺でさっぱりと - 2017.07.22
編集長のブログ47 夏は素麺でさっぱりと - 2017.07.22
梅雨もあけ、毎日暑い日が続いています。
こんなときの昼食は、冷たい麺類がいいですね。
今日は、大分の岸本満雄先生からこの夏に頂いた素麺を、具だくさんの五目素麺にしてみました。この「健彩麺」は十六穀入りで、健康に良いうえに、味も麺のコシもしっかりとしていて、とても美味しいのです。
岸本先生の奥様はとてもセンスが良いので、いろいろ探して選んでくださったのだと思います。

具が多すぎて麺が下のほうに少ししか見えません。栄養的には良いですが、せっかくの麺本来の美味しさを味わうためには、具はないほうが正解かもしれません。(岸本先生すみません!)
何でも、シンプルなものには本当の良さがあります。シンプルであればこそ、本物でないと通用しないともいえるでしょうか。
私たちの本作りも同様で、意味のない虚飾は私が最も嫌うところです。
 編集長のブログ46 「知の挑戦」ついに発刊! - 2017.07.13
編集長のブログ46 「知の挑戦」ついに発刊! - 2017.07.13
ようやく、ようやく、という感じで、感慨もひとしおです。

美しい装丁の、大変立派な本です。このような高級本は、今時は探すのが難しいくらいです。
もちろん、中身も立派です。

森先生が50年間、国際的な研究の場を駆け回った記録を、当地の地理や歴史も紹介しながら、ご自身で撮影した写真や当時の貴重な資料などを交え、旅日記も付してまとめた文献的価値の非常に高い一冊です。
森先生、お疲れ様でした。本当によく頑張られたと思います。
そして、『祝! 出版』 おめでとうございます。
 編集長のブログ45 歯科医師の重要性をアピールすることが必要 - 2017.06.03
編集長のブログ45 歯科医師の重要性をアピールすることが必要 - 2017.06.03
口腔内の専門職である歯科医師の重要性を、今まで以上にアピールしていく必要がある
5月31日厚生労働省において、第39回費用対効果評価専門部会、第133回薬価専門部会、第352回総会)が開催されました。中央社会保険医療協議会での議題「歯科医療(その1)について」において、遠藤秀樹委員(日歯常務理事)は以下のとおり意見を述べるとともに、質問を行いました。少し長いですが、非常に重要なテーマなので是非全文をお読みください。
歯科においては、これまで同様に、生活を支える医療として、「口腔機能の維持・向上により、国民の健康寿命の延伸とQOLの改善をはかる」ことを大きな目標としている。その中で、高齢者の外来受療率については、以前に比べて増加してはいるものの、要介護高齢者の7割で何らかの歯科治療の必要性があり、また高齢者の多くが「かみにくい」との自覚がありながら、通院率が低下する傾向が見られる。その理由は、アクセス、意識の問題等が考えられるが、理由が示されているのか伺いたい。また、要介護高齢者の場合は、本人の意向はなかなか把握しにくいこともあるため、本人と家族の意向に違いがあるか等データがあれば、示していただきたい。
高齢者の残存歯数は、国民の健康意識の向上や8020運動を通じてかなり増加してきているが、まだまだ不十分であり、更なる対応が必要と考える。1人当たりの歯科医療費でみると、一般成人では低下傾向にあるが、小児と高齢者で増加傾向にある。小児は、人口減少の中での増加であり、う蝕の減少の中でも健康意識が高まってきた結果であると思われる。高齢者は、医療単価(1日当たり歯科医療費)は横這いであるが、人口増と通院率の改善によるものと思われる。診療行為別調査においては、レセプト1件当たりの歯科医療費は減少傾向が続いているが、補綴部門の減少が大部分を占めている。これは、歯を残す治療や継続的な口腔管理による歯科疾患の軽症化によるものと考えられる。また、義歯の6か月規制や補綴物維持管理料の効果も一定程度含まれると考える。ただ、要介護者や認知症患者が増加する超高齢社会では、現在の社会状況に合わせて、これらの規制に在り方について見直す必要もあると考えられる。
かかりつけ歯科医機能においては、患者調査の結果から、6~7割にかかりつけ歯科医がいると認識していることが読みとれる。28年度改定では、かかりつけ歯科医の機能を評価していただいたわけだが、患者から「かかりつけ」と認識されている歯科診療所が、必要な機能を果たしていくことが重要と考えており、そのための環境整備や対応をさらに進めていきたい。
「かかりつけ歯科医機能」の実施状況から見ると、エナメル質初期加算は従来型の処置よりも高い実施率となっている。また歯周病安定期治療も増加傾向にあるが、新規設定されたⅡ型がまだ少ないのは、報酬が新たに包括化されたことが十分に周知されていない面もあると考えられる。また、患者は継続的管理や信頼性を評価しているものと考える。これらは通院患者のアンケート結果なので、この他に「かかりつけ歯科医機能」のもう一つの柱である在宅医療においても「か強診」が積極的に活動している。地域の医療連携においても、「か強診」のほうが積極的で、ミールラウンド等の介護関連の専門的な分野では特に高くなっており、まだスタートしたばかりの状態だが、その機能を果たしつつあると認識しており、さらに推進していく必要がある。
病院との連携における周術期口腔機能管理料に関しては、主として併設の病院歯科で実施されており、地域の歯科診療所が参加できる環境作りも重要である。300床以上の比較的大きな病院での算定が多いのは、病院歯科の設置の有無が差となっているものと考えられる。なお、都道府県により実施率に差があるが、郡市区歯科医師会レベルでの研修会等を積極的に実施して病院との連携を図っている地区は実施率が高いため、今後の活動の参考にしたい。
また、周術期口腔機能管理における連携効果として挙げられている全身麻酔の挿管時に歯が折れたり、抜けたりするといったトラブルを防止するためのプロテクター等は現状では評価されていないが、今後、対応の必要がある。
栄養サポートチームにおける低栄養への対応として口腔機能の改善は重要と考えられるが、周術期同様に比較的大きな病院で、院内の歯科医師との連携で算定されている。周術期共々、地域の歯科診療所と病院との連携にはまだまだ課題があるので、更なる対応を検討していきたい。
歯周病と糖尿病の関連をはじめとして、医科と歯科とで共同でみていく必要のある疾患が増えているが、しっかり対応できるような体制作りが必要であり、合わせて、医科と歯科の間での情報提供の在り方の検討も必要である。
口腔機能の維持向上の視点からは、幼児・学童期における「しっかり噛めない・食べられない」という発達不全や高齢者における機能低下への対応が求められる。超高齢社会におけるフレイルの概念の普及と共に、重要となってくる分野で、低栄養に関してもカロリーや栄養素と共に、必要とされる食事や食形態が摂食可能となるように「しっかり噛めること」を目指すなど、効果的な対応を検討していく必要がある。
これに対して、厚労省より「冒頭、質問のあった高齢者になると外来受療率が下がる件については、主に身体的理由だと思われるが、家族の意向と相違があるかと併せて、確認のうえ、検討・対応したい」旨、回答があった。
その他、1号側委員より、「全体的に年齢・階級別における残存歯数の増加やう蝕をはじめとする有病率の低下等、歯科の取組みは評価できる。今後、歯科に期待する役割としては、口腔機能管理を行うことによって歯周疾患の早期発見・早期治療、糖尿病等の重症化予防に寄与することが重要と考える。一方、歯科は医科と違い複数の診療所に通院することはなく、1か所に通院を続けると考えているといった意味でも、『かかりつけ歯科医機能』を有しているとも考えるので、地域包括ケアシステムへの参画、医科歯科連携の推進といった体制整備が喫緊の課題であると考える」、「『かかりつけ歯科医機能』については、28年度改定において十分な議論が行われないまま、評価されたと考えている。今回は、しっかり議論を行いたい。
また、現在、医政局において『かかりつけ歯科医機能』のイメージ等を検討しているのは、順序が逆ではないか。さらに地域包括ケアシステムにどう関わっていくのか不明である。口腔機能管理の評価等は重要であるが、地域包括ケアへの参画状況等においても、確かに『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』のほうが、一般歯科診療所より多いことが示されてはいるが、地域の在宅医療・介護を担う医療機関・事業所との連携等を行っていない『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』がまだまだ多く、施設要件にそういった連携を組み込むべきであると考える」、「『かかりつけ歯科医機能』に関して、国民の意識と診療報酬上の評価にはギャップがあると考えている。
国民は、『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』という理由で通院しているのではなく、いつも通院している歯科医院が『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』であったに過ぎないのではないか。また、歯周病安定期治療を行っても、『かかりつけ歯科医機能強化型診療所』では、患者が望んでいない口腔内写真の撮影が行われたり、患者負担額が違う等、患者のニーズに十分に応じていないうえ、歯科医療機関の差別化に繋がっていると考える。
一方、高齢化社会の中で口腔機能管理を行い、残存歯を増やしていることは評価できる。今後は、小規模な歯科診療所でも地域包括ケアの中で活躍できる体制を整備していくことが重要であると考える。」等といった意見が出された。
これに対し、遠藤委員は「『かかりつけ歯科医機能』については、目前に迫っている2025年に向けて早急に対応するための意味合いもあり同時進行で進める必要があったと考えている。今後、さらに検討・対応を図りながら推進していきたい。また、歯周用安定期治療においては、Ⅱの点数が高いのはⅠに検査等が新たに包括されているためで、分解すればほぼ同じ点数である。また、Ⅱを強制しているわけでなく、ⅠとⅡは選択性である。」と回答した。
また、丹沢秀樹専門委員より、「病院において栄養サポートチームに歯科医師を参画させることは重要であるが、大きな病院で院内に歯科医師が勤務していれば連携も取りやすいが、小さな病院で外部から歯科医師に参画してもらうには、評価が十分でない。一方、摂食機能においても、内科や神経内科だけでなく、口腔内の専門職である歯科医師の重要性を今まで以上にアピールしていく必要がある」との説明がなされました。